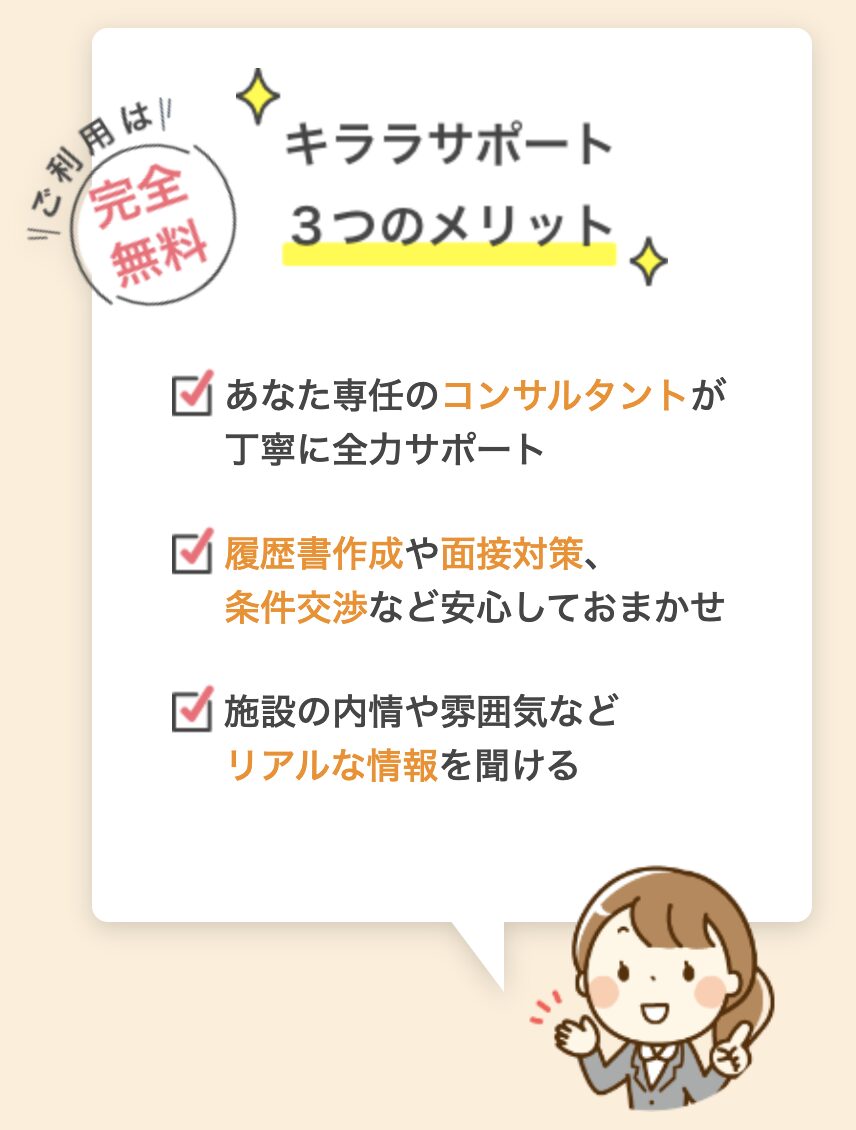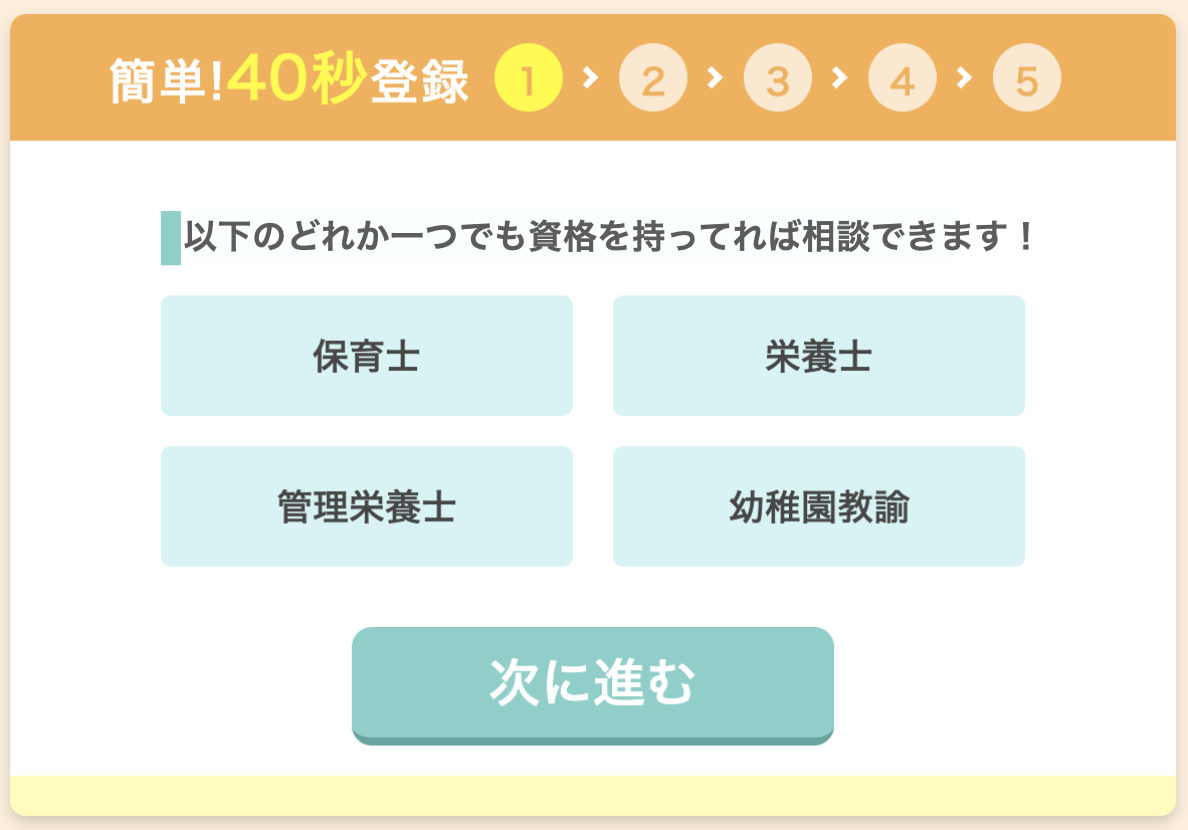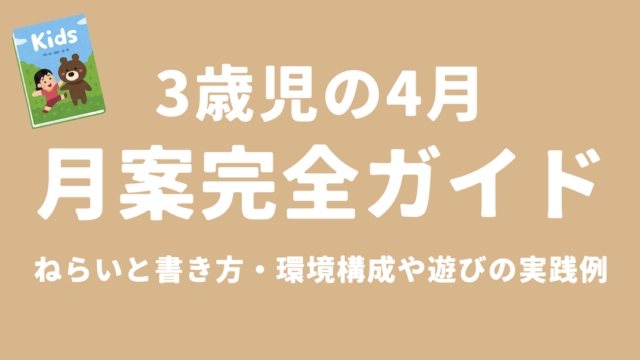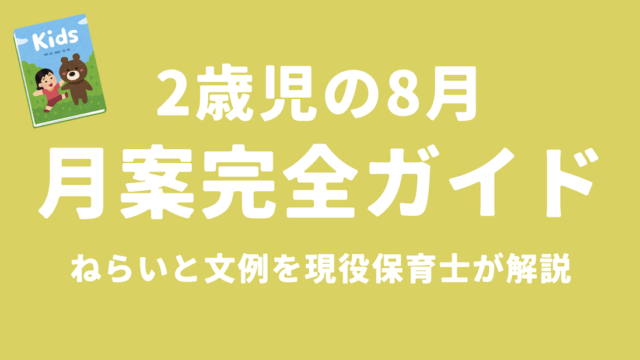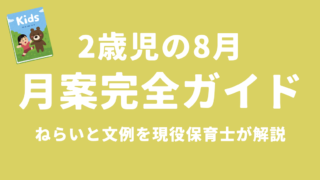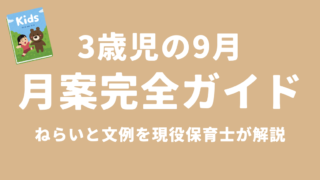【3歳児】11月の月案の書き方|ねらいと文例を現役保育士が徹底解説
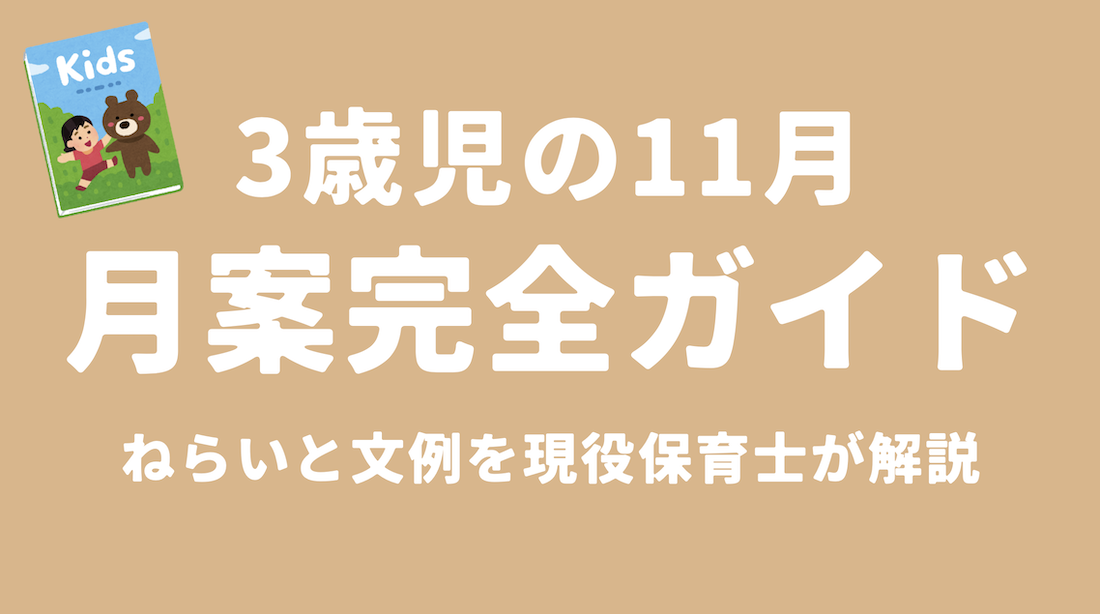
11月の3歳児向け月案作成に、頭を悩ませていませんか。
秋が深まり、子どもたちの成長に合わせて計画を見直す大切な時期ですが、「どのようなねらいを設定すれば良いのだろう」「具体的な活動例が思いつかない」と感じることも少なくありません。
この記事では、3歳児の11月の月案を作成する上で重要な、ねらいの設定から、養護の視点、そして子どもの姿の予測までを網羅的に解説します。
さらに、人間関係や言葉、表現といった発達領域ごとの配慮、排泄の自立支援、健康や安全の確保、食育の進め方についても触れていきます。
家庭との連携や保護者支援、円滑な職員との連携を実現するための環境構成、そして月末の評価反省のポイントまで、具体的な文例を交えながら分かりやすくご紹介します。
- 11月の3歳児に合った「ねらい」の設定方法
- 子どもの姿から考える具体的な活動内容
- 家庭や職員との連携で注意すべきポイント
- そのまま使える文例と書き方のコツ
3歳児の11月月案で押さえたい基本事項
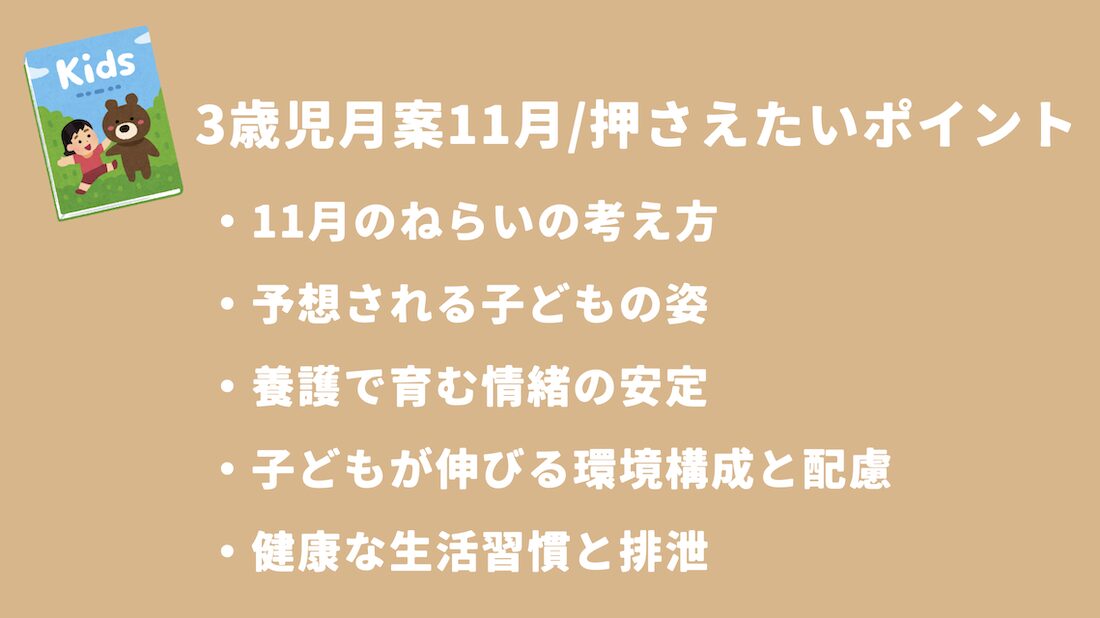
- 11月のねらいの考え方
- 予想される子どもの姿
- 養護で育む情緒の安定
- 子どもが伸びる環境構成と配慮
- 健康な生活習慣と排泄
11月のねらいの考え方
11月の月案における「ねらい」の設定は、子どもたちの成長を促すためのコンパスのような役割を果たします。結論として、この時期のねらいは、深まる秋の自然に親しみながら、友だちとの関わりを深め、生活習慣の自立へとつなげることが中心となります。
なぜなら、3歳児は言葉のやり取りが活発になり、友だちとイメージを共有して遊ぶ楽しさを感じ始める時期だからです。また、気温の変化とともに自身の健康に関心を持ち始める大切な段階でもあります。
具体的には、以下のような視点でねらいを設定すると良いでしょう。
教育面のねらい
落ち葉や木の実など、秋の自然物を使った遊びを通して、季節の変化を感じ、表現する楽しさを味わえるようにします。また、ごっこ遊びや簡単なルールのある集団遊びの中で、友だちと協力したり、気持ちを伝え合ったりする経験を促します。
養護面のねらい
気温の変化に合わせて衣服の調節を自ら意識できるように声をかけたり、感染症予防のために手洗いやうがいの習慣化を図ったりします。自分でできたという達成感が、さらなる自立へとつながります。
このように、子どもたちの発達段階と季節感を踏まえた多角的なねらいを設定することで、1ヶ月の保育活動がより豊かになります。
予想される子どもの姿
11月になると、3歳児クラスの子どもたちには心身ともに顕著な成長が見られます。月案を作成する上で、「予想される子どもの姿」を具体的にイメージしておくことは、適切な援助や環境構成を考えるための重要な土台となります。
この時期の子どもたちは、運動機能が向上し、友だちとの関わりがより密接になるため、遊びのスタイルも変化していきます。
例えば、以下のような姿が予想されます。
人間関係と遊びの広がり
気の合う友だちと一緒にごっこ遊びを楽しむ姿が増え、自分たちで物語を作りながら遊びを展開させていきます。「八百屋さんになってください」「じゃあ、私はお客さんね」といった具体的な役割分担も見られるでしょう。ただ、自己主張が強くなることで、イメージの違いから言い合いになる場面も出てきます。これは、相手の気持ちを理解しようとする成長過程の一つです。
自然への興味関心
散歩や戸外遊びでは、落ち葉の色の違いや形、木の実の種類に興味を示し、熱心に集める姿が見られます。「この葉っぱ、赤ちゃんの手に似てる!」といったユニークな表現も聞かれるかもしれません。集めた自然物を製作やおままごとに取り入れ、創造力を発揮します。
生活習慣の自立
衣服の着脱やボタンのかけ外しなど、身の回りのことを自分でやろうとする意欲が高まります。時間はかかりますが、保育者に見守られながら最後までやり遂げようと挑戦するでしょう。また、遊びに夢中になってトイレを忘れてしまうこともありますが、少しずつ自分のタイミングで排泄しようとする意識が芽生えます。
これらの姿を予測することで、保育者は「トラブルになった時にどう仲立ちするか」「集めた自然物を活かせるコーナーを用意しよう」といった具体的な配慮や計画を立てることができるのです。
養護で育む情緒の安定
3歳児にとって、園生活における情緒の安定は、あらゆる活動の基盤となる最も重要な要素です。養護の観点からは、子ども一人ひとりが「自分は大切にされている」「ここにいて良いんだ」と感じられるような、安心できる関わりと環境を保障することが求められます。
なぜなら、心が満たされている状態であってこそ、子どもは新しいことに挑戦したり、友だちと伸び伸びと関わったりする意欲が湧いてくるからです。特に、自己主張と他者意識の狭間で揺れ動くこの時期は、丁寧な寄り添いが不可欠です。
「自分でやりたい」という気持ちと「うまくできない」という葛藤がぶつかり合うのが3歳児です。その気持ちを丸ごと受け止めて、「ここまでできたね、すごいね」と過程を認めてあげることが、子どもの自己肯定感を育みます。
具体的な養護のポイントは以下の通りです。
- 受容的な関わり: 子どもの話にゆっくりと耳を傾け、気持ちを代弁します。「〇〇ちゃんは、もっと遊びたかったんだね」と言葉にしてあげることで、子どもは自分の気持ちを理解してもらえたと安心します。
- スキンシップ: 不安そうな時には優しく背中を撫でたり、できたことを褒める時に頭を撫でたりと、温かいスキンシップは言葉以上に子どもの心を安定させます。
- 落ち着ける空間の確保: 興奮したり疲れたりした時に、一人で静かに過ごせる絵本コーナーや、クッションのあるスペースを用意しておくことも大切です。子どもが自分で気持ちをクールダウンできる場所があることは、情緒の安定につながります。
子どもが伸びる環境構成と配慮
子どもたちの自発的な遊びや学びを引き出すためには、計画的で工夫された「環境構成」が欠かせません。保育者が行うべき配慮とは、単に安全を守るだけでなく、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを刺激し、試行錯誤を支える環境を整えることです。
なぜなら、3歳児は身の回りの様々なものに興味を持ち、それらを使って何かを試したいという探求心の塊だからです。魅力的な環境があることで、子どもは自ら関わり、遊びを発展させていきます。
コーナー保育の充実
子どもたちが自分の興味に合わせて遊びを選べるよう、ままごとコーナー、製作コーナー、絵本コーナーなどを明確に区切って設置します。11月は、製作コーナーに色とりどりの落ち葉や木の実、どんぐりなどを豊富に用意しておくと、子どもたちの創作意欲が自然と高まります。
遊びが連続するような工夫
例えば、ままごとコーナーの隣に、集めた自然物や廃材を置いた製作コーナーを設置します。すると、「どんぐりでご飯を作ろう」「落ち葉をお皿にしよう」といったように、コーナーを横断して遊びがダイナミックに展開していくことがあります。
安全への配慮
はさみやのりなどの道具を使う際は、正しい使い方を丁寧に伝え、保育者が側で見守れるような座席配置を工夫します。また、子どもたちが活動に集中できるよう、室内の動線が確保されているか、危険な箇所はないかを常に点検することが重要です。
このように、子どもの発達や興味を予測し、物的・空間的環境を戦略的に整えることで、保育者は子ども一人ひとりの主体的な活動を効果的に支えることができるのです。
健康な生活習慣と排泄
11月は、気温が下がり空気が乾燥するため、感染症が流行しやすい時期です。そのため、月案では子どもたちが健康な生活習慣を身につけられるような具体的な計画と、排泄の自立に向けた丁寧な支援を盛り込むことが極めて重要になります。
結論として、「なぜ手洗いやうがいが必要なのか」を子どもたちに分かりやすく伝え、自ら進んで行えるように促すことが目標となります。
手洗い・うがいの習慣化
ただ「洗いなさい」と指示するのではなく、手洗いの大切さが伝わる絵本を読み聞かせたり、「バイキンさんをやっつけようね」といった子どもがイメージしやすい言葉を使ったりする工夫が効果的です。水道の前にイラスト付きの手順を掲示するのも良いでしょう。ガラガラうがいが難しい子には、まずはブクブクうがいから丁寧に教えます。
衣服の調節
「寒いから」と厚着をさせがちですが、室内で活発に動くと汗をかき、それが冷えて体調を崩す原因にもなります。「暑いなと感じたら上着を脱ごうね」と声をかけ、子ども自身が快適な状態に気づき、調節しようとする意識を育てていくことが大切です。保育者は、一人ひとりの様子をよく観察し、個別に声をかける配慮が求められます。
排泄の自立に向けて
3歳児の排泄の自立は、個人差が非常に大きいテーマです。遊びに夢中になって失敗してしまうことも、成長の過程と捉え、決して叱らないようにしましょう。
大切なのは、決まった時間に誘うだけでなく、子どもが自分で尿意や便意に気づき、トイレに行けるようにサポートすることです。「おしっこ、行きたくないかな?」と問いかけ、自分の体の感覚に意識を向けられるように援助します。
3歳児向け11月月案の具体的な活動と連携
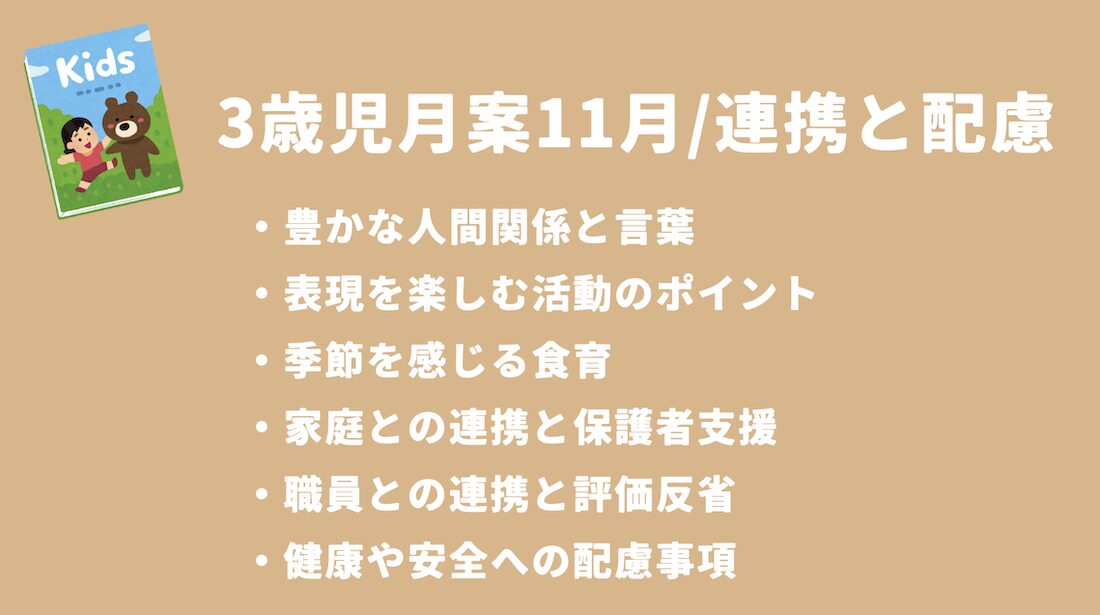
- 豊かな人間関係と言葉
- 表現を楽しむ活動のポイント
- 季節を感じる食育
- 家庭との連携と保護者支援
- 職員との連携と評価反省
- 健康・安全への配慮事項
豊かな人間関係と言葉
3歳児の11月は、友だちとの関わりの中で社会性が育まれ、言葉の能力が飛躍的に伸びる時期です。保育者は、子ども同士が豊かに関わり合えるような遊びを計画し、言葉のやり取りを楽しみながら語彙を増やしていけるよう援助することが求められます。
この時期の子どもたちは、自分の思いを言葉で伝えようとしますが、まだ語彙が十分でなかったり、相手の気持ちを想像したりすることが難しいため、トラブルも起こりがちです。しかし、その一つ一つの経験が、人間関係を築く力やコミュニケーション能力を育む大切な糧となります。
ごっこ遊びを通じた関わり
「お店屋さんごっこ」や「お医者さんごっこ」など、役割のあるごっこ遊びは、人間関係と言葉の発達を促す絶好の機会です。保育者は、子どもたちの会話に耳を傾け、「いらっしゃいませって言ってみようか」「次はどんなお客さんが来るかな?」などと、遊びが広がるような言葉を投げかけます。子ども同士のやり取りが滞っている場合には、さりげなく間に入って双方の気持ちを代弁し、コミュニケーションの橋渡しをします。
言葉の楽しさに触れる
絵本の読み聞かせは、新しい言葉や美しい日本語に触れる良い機会です。物語の世界に浸る中で、子どもたちは登場人物の気持ちを想像し、語彙を豊かにしていきます。また、「しりとり」や「ことばあつめ」などの言葉遊びもおすすめです。遊びの中で楽しみながら、言葉の響きや面白さに気づくことができます。
トラブルへの対応
おもちゃの取り合いなどのトラブルが起きた際は、まず両者の言い分をじっくりと聞くことが大切です。「貸してって言えたかな?」「順番で使おうか」など、具体的な解決策を子どもたち自身が考えられるように導きます。すぐに答えを示すのではなく、子どもたちが考え、話し合うプロセスを尊重する配慮が重要です。
表現を楽しむ活動のポイント
この時期の3歳児にとって、表現活動は自分の内面にある思いやイメージを外に出すための大切な手段です。歌や踊り、製作、描画といった活動を通して、子どもたちは言葉だけでは伝えきれない感情や考えを自由に表現する喜びを味わいます。
保育者は、上手・下手で評価するのではなく、子ども一人ひとりの表現そのものを認め、共感し、自信を持って楽しめるような雰囲気作りを心がけることが重要です。
秋の自然物を使った製作
公園で拾ってきた落ち葉やどんぐりは、最高の画材であり素材です。色とりどりの落ち葉を画用紙に貼り付けて動物の顔を作ったり、どんぐりや松ぼっくりで人形を作ったりと、自然物に触れる中で子どもたちの創造力は大きく広がります。
完成した作品をクラスのみんなで見せ合い、「このライオンさんのたてがみ、素敵だね」といったように、それぞれの工夫や発想を認め合う時間を持つことも大切です。
リズム遊びや劇あそび
音楽に合わせて体を動かすリズム遊びは、心と体を解放し、表現する楽しさを全身で感じる活動です。また、生活発表会に向けて、お気に入りの絵本を題材にした劇あそびを取り入れるのも良いでしょう。
子どもたちの表現は、大人の想像を超えるユニークなものばかりです。その子なりの表現を「面白いね」「素敵なアイデアだね」と肯定的に受け止めることで、子どもは安心して自分を表現できるようになります。
季節を感じる食育
11月は、サツマイモやキノコ、栗など、秋の味覚が豊富な季節です。食育活動を通して、子どもたちが旬の食材に親しみ、食べ物への感謝の気持ちを育む絶好の機会となります。
結論として、ただ食べるだけでなく、収穫したり調理に関わったりする体験を通して、食への興味・関心を深めることがこの時期の食育のねらいです。
例えば、以下のような活動が考えられます。
芋掘り体験とクッキング
園の畑で育てたサツマイモを収穫する体験は、子どもたちにとって大きな喜びです。土の感触や匂い、自分の手で掘り当てた時の達成感は、食材への愛着を育みます。収穫したサツマイモを使って、スイートポテトや芋版スタンプなど、簡単なクッキング活動に発展させるのも良いでしょう。自分たちが関わった食べ物は、苦手なものでも一口食べてみようという意欲につながります。
旬の食材に触れる
給食の時間に、「今日のお味噌汁には、秋においしいキノコが入っているよ」といったように、旬の食材について話す機会を設けます。本物の野菜や果物に触れさせ、匂いを嗅いだり、形を観察したりするだけでも、子どもたちの五感は刺激されます。七五三の行事食に触れ、日本の食文化に興味を持つきっかけ作りも大切です。
食事のマナーについても、少しずつ意識させていきたい時期です。「お茶碗をしっかり持って食べると、お米さんが喜ぶね」といったように、子どもが楽しく取り組めるような声かけを工夫しましょう。
家庭との連携と保護者支援
子どもの健やかな成長のためには、園と家庭が同じ方向を向いて協力し合う「連携」が不可欠です。特に、生活習慣や発達について変化が大きい3歳児の時期は、日々の様子を密に共有し、保護者の不安や悩みに寄り添う支援が求められます。
なぜなら、園での子どもの姿と家庭での姿は違うことも多く、両方の情報を合わせることで、その子への理解がより深まるからです。また、保護者が安心して子どもを預けられる信頼関係を築くことが、子どもの情緒の安定にもつながります。
具体的な連携と支援の方法は以下の通りです。
| 連携・支援の方法 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 連絡帳や口頭での情報共有 | その日の体調や機嫌だけでなく、「今日はお友だちと〇〇ごっこで盛り上がっていました」「ブロックでこんなに高いタワーが作れましたよ」といった具体的なエピソードを伝えます。これにより、保護者は園での子どもの様子を生き生きとイメージできます。 |
| クラスだよりや掲示物 | クラス全体の活動の様子や、11月のねらい、感染症対策についてなどを知らせます。子どもたちが作った作品を掲示し、その子の発想の面白さや工夫した点をコメントで添えると、保護者の喜びもひとしオです。 |
| 保護者の悩みへの対応 | 「家でわがままを言って困る」「好き嫌いが多い」といった保護者の悩みに対して、専門的な視点からアドバイスをしたり、園での様子を伝えて安心感を持ってもらったりします。大切なのは、保護者の気持ちに共感し、一緒に考えていく姿勢です。 |
衣替えや持ち物に関するお願い
寒暖差が激しくなるため、着脱しやすく体温調節ができる衣服の用意をお願いします。また、芋掘り遠足などの行事がある場合は、持ち物について早めに、そして分かりやすく伝える配慮が必要です。
職員との連携と評価反省
質の高い保育を提供するためには、クラス担任だけでなく、他の職員との円滑な「職員間連携」が欠かせません。日々の保育の様子や子どもの情報を密に共有し、チームとして一貫した対応を行うことが重要です。
また、月末には計画通りに保育が実践できたか、子どもの成長にどのような影響があったかを振り返る「評価反省」を行い、次の月の計画に活かしていく必要があります。
日々の情報共有
朝のミーティングや職員間の連絡ノートなどを活用し、「〇〇ちゃんが昨日から咳をしている」「△△くんがお友だちとの関わりで悩んでいるようだ」といった個別の情報を全職員で共有します。これにより、どの職員でも適切に対応できるようになります。また、子どもたちの面白いエピソードや成長を感じた瞬間を共有することは、職員同士のモチベーション向上にもつながります。
行事に向けての協力
生活発表会や作品展などの行事に向けては、各クラスの進捗状況を報告し合い、会場準備や役割分担などを計画的に進める必要があります。クラスの垣根を越えて協力し合う体制を築くことが、行事の成功につながります。
評価反省の視点
月末の評価反省では、以下の点を振り返ります。
- 設定した「ねらい」は、子どもたちの実態に合っていたか。
- 計画した活動は、子どもたちの興味を引き出し、主体的な参加を促せたか。
- 環境構成や保育者の援助は適切だったか。
- 子どもたちはどのような点で成長が見られたか。
- 改善すべき点や、来月の計画に活かすべきことは何か。
評価反省は、単なる「できた・できなかった」の確認ではありません。子どもの姿を丁寧に見つめ直し、保育の質を向上させていくための大切なプロセスなのです。
健康・安全への配慮事項
子どもたちが毎日安心して楽しく園生活を送るためには、健康・安全管理がすべての基本となります。11月は、感染症の流行や、活発になる身体活動に伴う怪我のリスクなど、特に注意が必要な時期です。
保育者は、考えられる危険を予測し、未然に防ぐための環境整備と指導を徹底しなければなりません。
感染症対策
前述の通り、インフルエンザをはじめとする感染症の予防が最重要課題です。手洗い・うがいの指導に加え、室内の適切な換気や湿度管理、おもちゃの定期的な消毒などを徹底します。子どもの体調変化にいち早く気づけるよう、登園時の視診を丁寧に行い、少しでも普段と違う様子があれば保護者と連携を取ります。
戸外活動での安全確保
ボールや鉄棒、縄跳びなど、様々な遊具を使った遊びに挑戦する時期ですが、運動機能の発達には個人差があります。遊具の正しい使い方を伝え、危険な動きをしていないか常に注意を払う必要があります。また、芋掘り遠足などで園外に出る際は、事前に下見を行い、危険箇所や交通ルールを職員間で確認しておくことが不可欠です。
誤飲の防止
どんぐりや木の実など、秋の自然物は子どもたちにとって魅力的ですが、乳児クラスではない3歳児でも誤飲のリスクはゼロではありません。特に小さな自然物を製作で使う際は、口に入れたり鼻に入れたりしないよう、活動中は側で見守る体制を整えます。
これらの健康・安全への配慮は、月案の段階で具体的に計画し、全職員で共通認識を持って取り組むことが大切です。
3歳児の11月月案作成の総まとめ
- 11月のねらいは秋の自然、友だちとの関わり、生活習慣の自立が中心
- 子どもの姿として遊びの広がりや自然への興味、自立心の高まりを予測する
- 養護の基本は子どもの気持ちを受容し、情緒の安定を図ること
- 環境構成は子どもの「やってみたい」を刺激するコーナー保育が有効
- 健康管理では感染症予防として手洗いやうがいの習慣化を目指す
- 排泄は子どものタイミングを尊重し、成功体験を積ませることが重要
- 人間関係はごっこ遊びなどを通じて育み、トラブルは成長の機会と捉える
- 言葉の発達は絵本の読み聞かせや言葉遊びで促す
- 表現活動では結果よりプロセスを認め、子どもの自信を育てる
- 食育は収穫体験などを通して食べ物への興味関心を深める
- 家庭との連携では日々の具体的なエピソードを共有し信頼関係を築く
- 保護者支援では悩みに寄り添い、一緒に考える姿勢が大切
- 職員間連携では日々の情報共有と行事への協力体制が不可欠
- 評価反省を行い、子どもの成長を振り返り次月の計画に活かす
- 安全対策として遊具の点検や誤飲防止を徹底する

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。
しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。
また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。
選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。
参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。
厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。
少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。
地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。
そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。
参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?