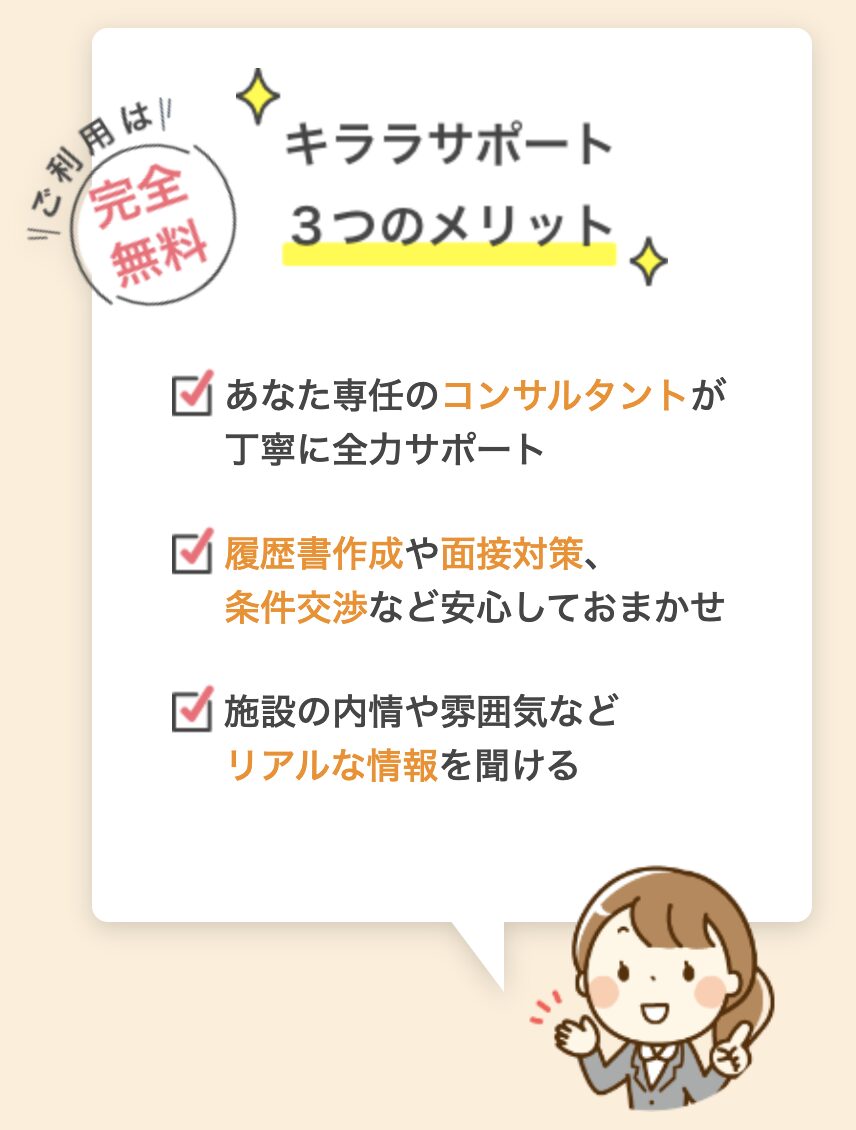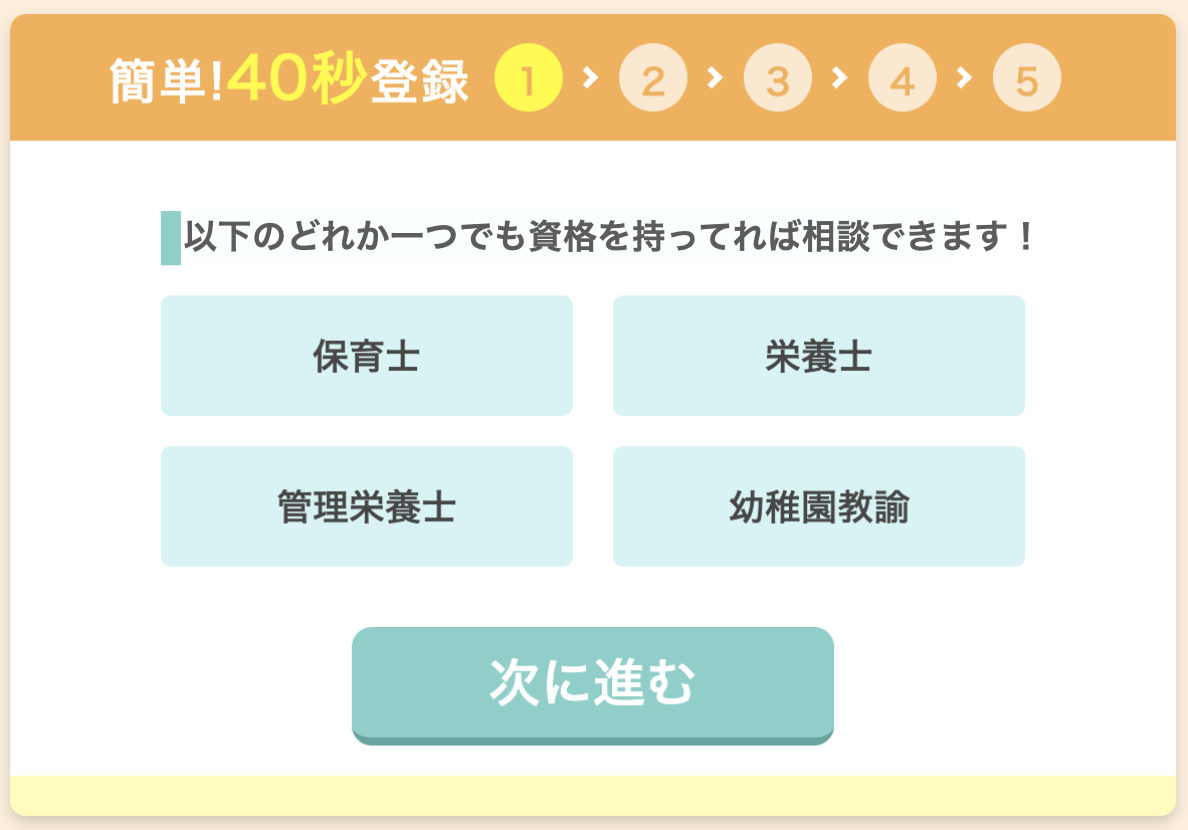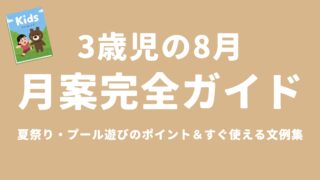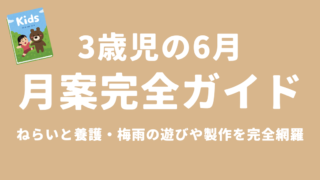3歳児の7月月案作成ガイド!ねらいや水遊び・行事の書き方例
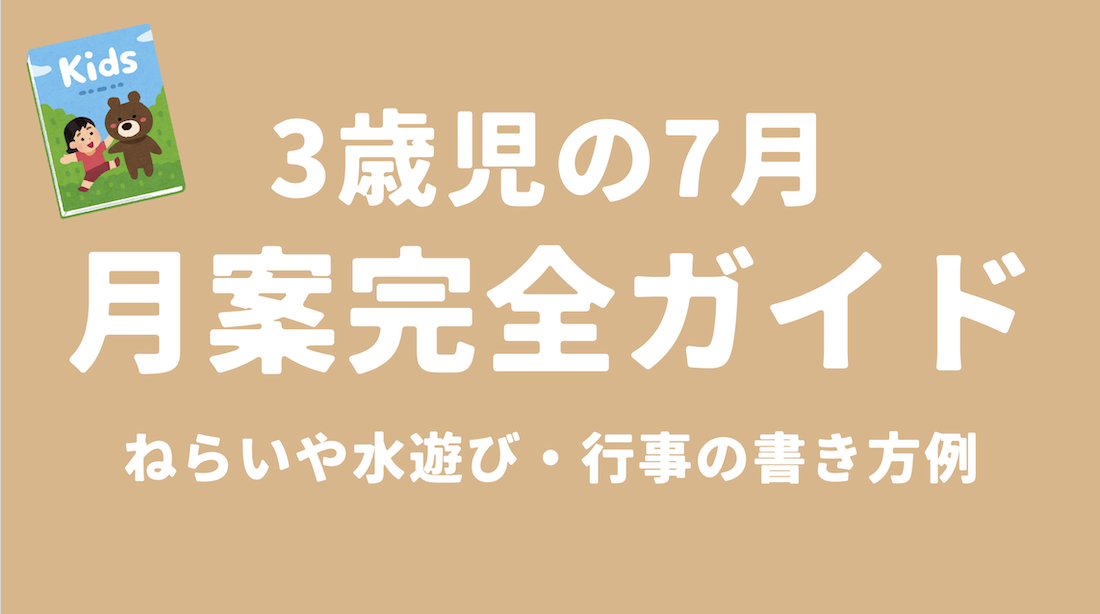
梅雨が明けて本格的な夏が到来する7月は、プール開きや七夕、夏祭りなど、子どもたちがワクワクする行事が目白押しですね。
3歳児クラスの子どもたちは、新しい環境にも慣れて活発になる一方で、暑さによる疲れや感染症のリスクも高まる時期です。
そんな中で、3歳児の7月月案を作成するにあたっては、どのようなねらいを設定し、どんな点に配慮すべきか悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。
今回は、水遊びや泥んこ遊びといった夏ならではの活動内容や環境構成、予想される子どもの姿への援助、そして具体的な書き出しや5領域に基づく指導計画の文例まで、幅広く解説していきます。
食育や反省のポイントも押さえて、実りのある夏を過ごせるような月案作りを一緒に考えていきましょう。
- 3歳児の7月月案における「養護」と「教育」の具体的なねらいとバランスがわかります
- 水遊びや泥んこ遊びの環境構成と、安全管理や感染症対策のポイントが整理できます
- 季節感のある月案の書き出し文例や、5領域ごとの具体的な指導内容を知ることができます
- 保護者連携や食育、次月につなげる反省の視点まで、月案作成の全体像を把握できます
3歳児の7月月案で意識すべきねらいと配慮
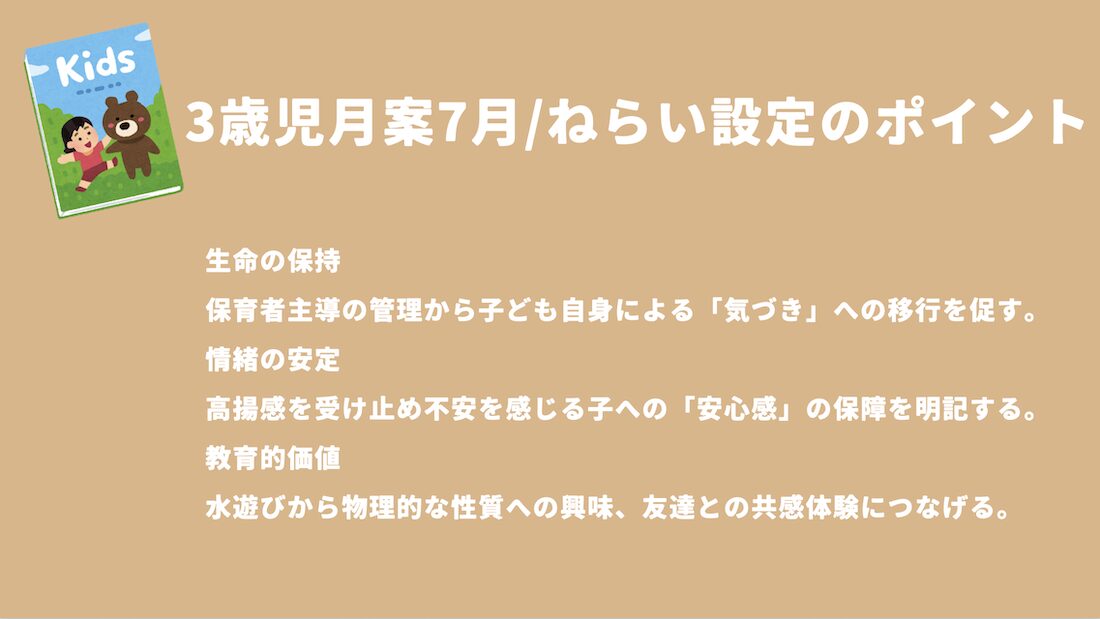 7月の3歳児クラスは、4月の入園・進級から3ヶ月が経ち、集団生活にも慣れて自我が大きく育つ時期です。一方で、急激な気温上昇による体調変化や、開放的な遊びによる興奮など、保育者がコントロールすべき要素が格段に増える月でもあります。
7月の3歳児クラスは、4月の入園・進級から3ヶ月が経ち、集団生活にも慣れて自我が大きく育つ時期です。一方で、急激な気温上昇による体調変化や、開放的な遊びによる興奮など、保育者がコントロールすべき要素が格段に増える月でもあります。
では、この時期特有の「3歳児 7月 月案」を作成する上で、中心となるねらいの設定や、夏ならではの活動における配慮点について、発達心理学的な視点も交えながら詳しく見ていきましょう。
養護と教育の視点からねらいを設定する
7月の月案作成において最も重要なのは、「過酷な夏の環境から身を守る(養護)」ことと、「夏ならではのダイナミックな体験を保障する(教育)」ことのバランスです。この2つは相反するものではなく、相互に作用し合うものとして捉える必要があります。
養護:生理的欲求への気づきと情緒の安定
まず「養護」の視点ですが、最優先事項はもちろん「生命の保持」です。3歳児は遊びに没頭すると、身体的限界を超えて動き続けてしまう傾向があります。「喉が渇いた」「疲れた」という身体からのサインを、子ども自身がまだ十分にキャッチできない、あるいは無視してしまうことが多いのです。
そのため、ねらいとしては単に「健康に過ごす」とするだけでなく、「保育者の促しにより、水分補給や休息を行い、心地よく過ごす」といった記述が基本になります。さらに一歩進んで、「汗をかいたら着替える」「喉が渇いたらお茶を飲む」といった行動を通して、自分の体の状態に気づく(自覚する)ことへの橋渡しを意図したねらいも重要です。
また、情緒面も見逃せません。プールや水遊びは楽しい反面、水への恐怖心がある子や、騒がしい環境が苦手な子にとっては大きなストレス源になり得ます。「夏の開放的な雰囲気の中で、保育者に自分の気持ちを受け止めてもらいながら安心して過ごす」というねらいを設定し、興奮と不安が入り混じる子どもたちの心の安全基地(セキュアベース)としての役割を明記しましょう。
教育:感覚の開放と他者意識の芽生え
「教育」の視点では、5領域の「環境」や「人間関係」が色濃く出ます。この時期の子どもたちは、言葉で表現しきれない情動を抱えています。水、泥、泡といった不定形の素材に触れる感覚遊び(センサリープレイ)は、言葉にならない感情を開放し、情緒を安定させるセラピー的な効果も期待できます。
ねらいの具体例としては、「水や泥などの夏の自然事象に触れ、その感触や変化を全身で楽しむ」などが挙げられます。また、プールなどの共有体験を通じて「冷たいね!」「気持ちいいね」といった共感が生まれやすい時期でもあります。「友達と同じ遊びをする楽しさを味わい、関わりを深める」といった人間関係のねらいも、7月には欠かせない要素です。
ねらい設定のポイント
- 生命の保持:保育者主導の管理から、子ども自身による「気づき」への移行を促す。
- 情緒の安定:高揚感を受け止めつつ、不安を感じる子への「安心感」の保障を明記する。
- 教育的価値:単なる水遊びで終わらせず、物理的な性質への興味や、友達との共感体験につなげる。
水遊びや泥んこ遊びの活動内容と環境構成
3歳児にとっての水遊びや泥んこ遊びは、単なる「涼をとるための活動」ではありません。水が流れる様子、泥の重さ、乾いた砂との違いなど、物理法則(浮力、抵抗、流体)を肌で感じる科学的探究の場です。月案に記載する活動内容と環境構成は、子どもの探究心を支えつつ、安全を確保する緻密な設計が求められます。
段階的な活動内容の展開(スモールステップ)
活動内容は、子どもの実態に合わせて段階的に計画します。いきなり大きなプールに入るのではなく、以下のようなステップを想定しておきましょう。
- 導入期(水に慣れる):まずはタライやビニールプールに浅く水を張り、手でパシャパシャと触れることからスタートします。ジョウロやカップ、ペットボトルのシャワーなど、「道具」を介在させることで、水への直接的な恐怖心を和らげることができます。
- 展開期(全身を使う):水に慣れてきたら、ワニ歩き(水底に手をついて進む)や、顔つけ(一瞬水に顔をつける)に挑戦します。ここでは「できた・できない」を評価するのではなく、「やってみようとする意欲」を大切にします。
- 発展期(泥んこ・構成遊び):水だけでなく、土や砂と組み合わせた泥んこ遊びへ発展させます。「泥団子作り」や「チョコレート屋さんごっこ」など、泥の可塑性(形が変わる性質)を利用した見立て遊びは、想像力を大きく育てます。
安全と自立を促す環境構成
環境構成で最も意識すべきは「動線」と「ゾーニング」です。濡れた体で移動することは転倒リスクを高めるため、プールからシャワー、着替え場所、トイレへの動線には、必ず滑り止めマットを敷きましょう。
また、着替えの環境も重要です。3歳児は自分で着替えようとする意欲が高まっていますが、濡れた水着を脱ぐのは大人でも難しいものです。着脱しやすい広めのスペースを確保し、脱いだ服が散乱しないよう、一人ひとりのカゴをわかりやすく配置するか、着替える場所(濡れたゾーン)と着替え終わった場所(乾いたゾーン)をビニールテープなどで視覚的に区切る工夫が有効です。
さらに、「静と動のバランス」を保つための環境設定も忘れてはいけません。プール遊びで興奮した後に、クールダウンして過ごせる「カームダウンエリア(静かな絵本コーナーやテントなど)」を室内に常設しておくことで、子どもたちの情緒の安定を図ることができます。
環境構成のチェックリスト
- プールサイドの監視位置(死角がないか)
- 滑り止めマットの設置範囲
- 休憩用日陰(シェードやテント)の確保
- 玩具の数量(取り合いを防ぐため多めに用意)
- 温水シャワーの温度設定と水圧確認
予想される子どもの姿と個別の援助
夏の開放感は、子どもたちの「個」を浮き彫りにします。活発になる子もいれば、環境の変化に戸惑う子もいます。月案には、ポジティブな姿だけでなく、課題となる姿も具体的に予想し、プロとしての援助方針を記載しておくことが大切です。
水への抵抗感がある子への配慮
「水が顔にかかるのが怖い」「泥で手が汚れるのが嫌だ」という感覚過敏を持つ子もいます。こうした子に対して、「みんな入っているから頑張ろう」と無理強いするのは逆効果です。
援助の具体例としては、「プールサイドでタライ遊びを楽しむ」「足だけ水につけてみる」といった別メニューを用意し、スモールステップで誘うことが基本です。「先生と一緒に足だけパシャパシャしてみようか」と提案したり、好きな玩具を見せて興味を引いたりしながら、安心できる関係性の中で少しずつ許容範囲を広げていけるようにします。「見学」という選択肢も尊重しつつ、決して孤独にさせない配慮が必要です。
興奮してルールが守れない場面への対応
逆に、楽しすぎて興奮し、プールサイドを走ったり、友達に水をかけ続けたりする姿も予想されます。これらは悪意があるわけではなく、自己制御機能が未熟なために起こる行動です。
ここでは、「走らない!」「ダメ!」と禁止語だけで注意するのではなく、事前に視覚的なルール提示を行うのが効果的です。走ってはいけない場所をイラストで示したり、「忍者みたいにそろりそろりと歩こうね」と遊びの要素を取り入れた言葉がけをしたりしてみましょう。また、ヒートアップしている子には、一度プールから上がってクールダウンする時間を設けるなど、物理的に落ち着ける環境を作る援助も必要です。
トラブルを通じた社会性の育ち
3歳児は「並行遊び」から、友達と関わって遊ぶ「連合遊び」へと移行する過渡期です。水遊びの玩具(ジョウロやバケツなど)を巡る取り合いは頻発するでしょう。
このトラブルを単なる「喧嘩」として処理するのではなく、社会性を育むチャンスと捉えます。保育者が仲立ちとなり、「貸してって言ってみようか」「今使っているから、あとでねって伝えよう」と、具体的な言葉のモデルを示します。「貸して」と言えたこと、「いいよ」と貸せたこと、あるいは「待てたこと」を具体的に認め、承認することで、子どもたちは人との関わり方を学んでいきます。
夏の感染症や熱中症対策への配慮事項
7月の保育において、危機管理は活動計画と同じくらい重要です。特に「熱中症」と「夏の感染症」は、子どもの命と健康に直結するリスクであり、経験則ではなく客観的な基準に基づいた管理が求められます。
熱中症対策:WBGT(暑さ指数)の厳格な運用
近年、猛暑日が増加しており、気温だけを基準にした判断では不十分です。環境省が推奨するWBGT(暑さ指数)を基準に行動を決定することが、保育現場のスタンダードになりつつあります。
月案の配慮事項には、「WBGTの実測値を基に、活動の短縮や中止を判断する」と明記しましょう。具体的には、WBGTが「厳重警戒(28〜31℃)」レベルに達した場合、激しい運動は中止し、プール活動も日除けの下で短時間(15分程度)に行う、といったルールを徹底します。また、子どもは大人よりも身長が低く、地面からの照り返し(輻射熱)を強く受けるため、大人の感覚よりも高温の環境にいることを忘れてはいけません。
参考データ:熱中症予防のための運動指針
環境省の熱中症予防情報サイトでは、日常生活や運動時における具体的な指針が示されています。保育活動においても、この基準を参考に、気温・湿度・輻射熱を総合的に判断する必要があります。
夏の感染症:視診と衛生管理の徹底
プール熱(咽頭結膜熱)、手足口病、ヘルパンギーナといった夏風邪は、感染力が非常に強く、集団生活ではあっという間に広がります。
毎朝の「視診」を強化し、発疹の有無、目の充血、普段と違う機嫌の悪さなどをチェックします。特に手足口病は、口の中の水疱が痛くて食事が摂れないことがあるため、給食時の様子(食べるのが遅い、痛がるなど)も重要な観察ポイントです。
プール活動においては、水の衛生管理が必須です。残留塩素濃度の測定を必ず行い、基準値(0.4mg/L〜1.0mg/L程度)を維持すること、タオルの共用を絶対に避けること、活動後のシャワーと洗眼を徹底することを、職員間で再確認し、月案にも「衛生管理の徹底」として記載しておきましょう。
七夕製作や行事を月案に取り入れる
7月7日の七夕は、子どもたちが日本の伝統文化や季節感に触れる絶好の機会です。しかし、3歳児にとって「星に願いを込める」という概念や、織姫と彦星の物語は少し抽象的で理解が難しい部分もあります。月案に取り入れる際は、発達段階に合わせたアプローチが重要です。
物語の世界への導入
まず、行事の意味を伝える導入として、視覚的な教材を活用します。ペープサートやパネルシアター、大型絵本などを使い、「織姫さまと彦星さまが、一年に一度だけ会える日なんだよ」というストーリーをわかりやすく伝えます。3歳児は「会いたい人に会える」というテーマに共感しやすく、物語を通して行事への期待感を高めることができます。
また、七夕の歌(「ささのはさらさら」など)を日常的に歌うことで、聴覚からも季節感を取り入れましょう。歌詞に出てくる「五色の短冊」などの言葉に触れることも、言葉の領域(語彙の獲得)につながります。
指先の発達を促す製作活動
七夕飾りなどの製作は、微細運動(手先の器用さ)を養う教育的な活動です。3歳児の7月であれば、以下のような技法を取り入れた製作がおすすめです。
- 三角つなぎ・四角つなぎ:折り紙をのりで繋げていく活動です。「端っこにのりをつける」という空間認知能力や、指先のコントロールを養います。長く繋がっていく様子に達成感を感じやすい活動です。
- シール貼りやなぐり描き:スイカや魚などの形に切った画用紙に、シールで模様をつけたり、マーカーで自由になぐり描き(スクリブル)をしたりします。自分だけの作品を作る喜びを味わいます。
- 染め紙:障子紙を折って色水に浸す染め紙は、色が混ざり合う不思議さや、広げた時の模様の美しさに気づく「感性」を育む活動です。
短冊の願い事については、まだ文字が書けない子がほとんどですので、保護者に代筆をお願いすることが一般的です。しかし、シールを貼ったり、自分で選んだ色の短冊を使ったりすることで、「自分が参加した」という実感を持たせる工夫をしましょう。飾る際は、子どもの手が届く高さに笹を設置し、自分で飾る体験を保障することも大切です。
実践に役立つ3歳児の7月月案の書き方と反省
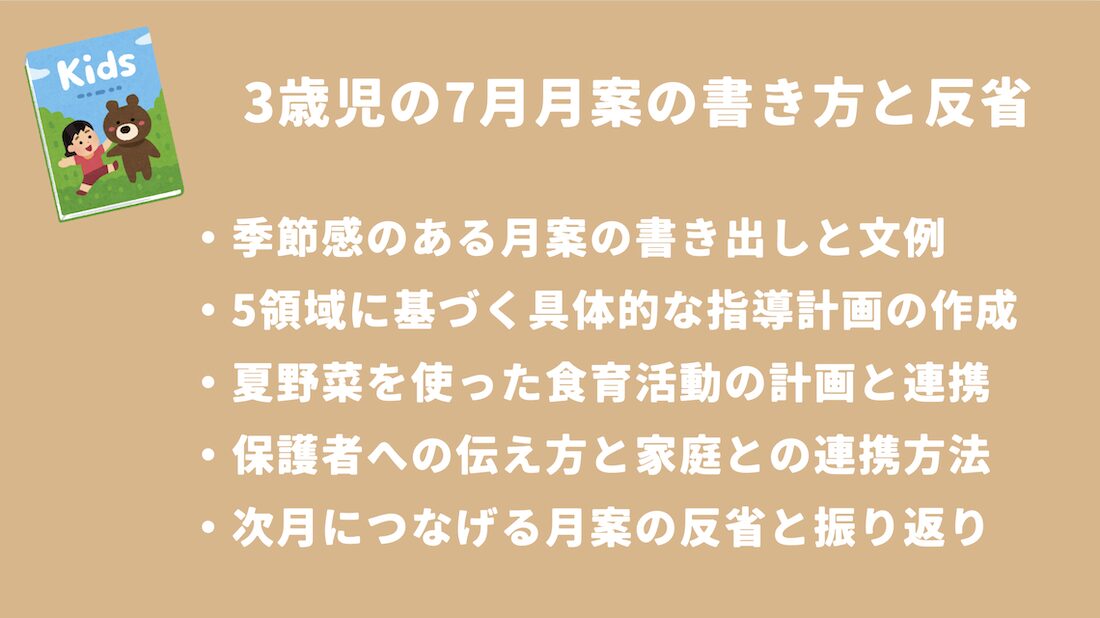
理論だけでなく、実際の書類作成ですぐに使える実践的なテクニックを解説します。保育士さんにとって、毎月の月案作成は時間との戦いでもありますよね。
「3歳児 7月 月案」を作成する際に迷いがちな書き出しのバリエーションや、5領域に基づいた具体的な記述例、食育や保護者対応のポイントを詳細にまとめました。
季節感のある月案の書き出しと文例
月案の冒頭(導入文・前文)は、その月のクラスの雰囲気や季節感を伝える「顔」となる部分です。単に「暑くなりました」だけでなく、子どもたちの具体的な姿や、五感を使った表現を入れると、読み手(園長や主任、あるいは保護者)にクラスの現状が生き生きと伝わります。
初旬・梅雨明け前後の書き出し
- 「長かった梅雨もようやく明け、園庭にはまぶしい太陽の光が降り注いでいます。子どもたちは『今日プール入れる?』と毎朝保育者に問いかけ、水遊びへの期待に胸を膨らませています。」
- 「蒸し暑い日が続いていますが、額に汗を光らせながら元気に遊ぶ子どもたち。七夕の笹飾りが風に揺れるのを見て、『きれいだね』と指差す姿に、感性の育ちを感じるこの頃です。」
中旬・夏本番の書き出し
- 「セミの大合唱と共に、本格的な夏がやってきました。水遊びや泥んこ遊びでは、水しぶきを浴びて歓声を上げ、全身で夏の感触を楽しんでいる子どもたちです。」
- 「水遊びを通じて、着替えや準備の流れが少しずつ身についてきました。『自分でやる!』と意欲的に取り組む姿に、一学期の成長を感じます。暑さに負けず、一人ひとりがたくましく活動しています。」
健康・休息に触れる書き出し
- 「夏の暑さで疲れが出やすい時期となりました。休息と活動のバランスに十分に配慮し、ゆったりとした時間の中で安心して過ごせるよう環境を整えていきたいと思います。」
- 「汗を拭いたり水分を摂ったりする心地よさを、子どもたち自身が感じ始めています。健康管理に留意しながら、夏ならではのダイナミックな遊びを存分に楽しんでいきたいです。」
5領域に基づく具体的な指導計画の作成
5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)に基づいた指導計画は、それぞれが独立しているのではなく、一つの遊びの中で相互に関連し合っています。
3歳児の7月に想定される具体的な内容を、ねらい・内容・環境構成に分けて表にまとめました。自園の書式に合わせて活用してください。
| 領域 | ねらい(目指す姿) | 内容(活動・経験) | 環境構成・配慮 |
|---|---|---|---|
| 健康 | ・水遊びの約束を知り、安全に気をつけて遊ぶ。 ・汗や汚れを意識し、清潔にする心地よさを味わう。 ・休息や水分補給の必要性に気づく。 |
・保育者の声かけで水分補給をする。 ・プールサイドでは走らない等のルールを守ろうとする。 ・濡れた服を着替え、さっぱりする。 |
・着替えやすいスペースの確保。 ・お茶を飲みやすい場所に設置。 ・視覚的なルール表示。 |
| 人間関係 | ・保育者や友達と同じ遊びをする楽しさを味わう。 ・玩具の貸し借りを通じ、関わりを深める。 |
・「入れて」「貸して」と言葉や仕草で伝える。 ・友達と水の冷たさを共有し、笑い合う。 ・順番を守ろうとする。 |
・十分な数の玩具を用意。 ・トラブル時は双方の気持ちを代弁する仲立ちを行う。 |
| 環境 | ・水、泥、泡などの性質に興味を持ち、試行錯誤して遊ぶ。 ・夏の動植物に関心を持つ。 |
・泥の感触を楽しむ。 ・色水遊びで色の変化に気づく。 ・園庭のセミやアサガオを観察する。 |
・プリンカップやペットボトル等の廃材容器の準備。 ・虫眼鏡や図鑑の配置。 |
| 言葉 | ・発見や感動を言葉で表現しようとする。 ・保育者の言葉かけに応答し、やり取りを楽しむ。 |
・「冷たい!」「見て!」と伝える。 ・七夕の物語や絵本を楽しむ。 ・「貸して」「いいよ」のやり取り。 |
・子どもの感動を具体的な言葉(「冷たくて気持ちいいね」等)で代弁する。 ・季節の絵本の用意。 |
| 表現 | ・イメージを形にしたり、身体全体で表現したりする。 ・音楽に合わせてリズム遊びを楽しむ。 |
・七夕飾り作りで指先を使う。 ・「おばけなんてないさ」等の歌を歌う。 ・水や泥で自由な形を作る。 |
・扱いやすい素材(シール、のり)の準備。 ・開放的なスペースでのリズム遊び。 |
夏野菜を使った食育活動の計画と連携
夏は色鮮やかな野菜(トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシ、オクラなど)が旬を迎え、食育活動に最適なシーズンです。3歳児クラスでは、栽培や収穫だけでなく、「食材に触れる」体験を重視することで、食への関心を高め、偏食の改善につなげるねらいがあります。
トウモロコシの皮むき体験
3歳児に特におすすめなのが、トウモロコシの皮むきです。これは単なるお手伝いではなく、以下のような教育的意義があります。
- 指先の発達:一枚ずつ皮をむく動作には、指先の力とコントロールが必要です。
- 五感の刺激:皮のざらつき、ヒゲの感触、青臭い匂い、実の鮮やかな黄色など、五感をフルに使って観察できます。
- 自己有用感:「みんながむいてくれたから、今日の給食は特別美味しいね」と声をかけることで、「自分が役に立った」という自信につながり、苦手な子も一口食べてみようとするきっかけになります。
野菜スタンプによる造形活動
食べるだけでなく、野菜の形を楽しむ活動として「野菜スタンプ」も人気です。オクラ(星形)、レンコン(穴あき)、ピーマン(空洞)、小松菜の根元(バラの花の形)など、野菜の断面は個性的で美しい模様を持っています。
絵の具をつけて画用紙に押すことで、模様の面白さに気づくだけでなく、押す力の加減を調整する感覚も養います。活動の前には、調理スタッフと連携して、廃棄する部分(切れ端)を提供してもらえるよう調整しておきましょう。また、誤食を防ぐための安全管理(「これはスタンプ用だから食べないよ」という約束)も徹底します。
保護者への伝え方と家庭との連携方法
夏の保育を安全かつスムーズに進めるためには、保護者の理解と協力が不可欠です。月案の「家庭との連携」欄には、事務的な連絡だけでなく、子どもの成長を共有し合うための具体的な依頼事項を記載します。
健康管理の協力依頼
プールや水遊びに参加するためには、毎朝の健康観察が必須です。「プールカード(参加確認票)」への記入をお願いすることになりますが、これは単なる事務手続きではありません。「朝、お子さんの顔色を見て、熱を測って、体調を確認すること」自体が、事故防止の第一歩であることを伝えましょう。「少しでも体調に不安がある日は、無理せず見学を選んでください」というメッセージも重要です。
生活リズムと疲労への配慮
夏の遊びは体力を激しく消耗します。園で全力で遊んでいる分、家ではぐずったり食欲が落ちたりすることもあるでしょう。「園でたくさん体を動かしているので、ご家庭では早めの就寝を心がけ、ゆったり甘えさせてあげてください」といった具体的なアドバイスをおたよりや送迎時の会話で伝えます。
洗濯物への感謝と配慮
夏の間は、毎日水着やタオルを持ち帰るため、保護者の洗濯負担が増大します。おたよりの一文に「毎日のお洗濯やご準備、本当にありがとうございます。清潔な衣服のおかげで、子どもたちは気持ちよく過ごせています」と感謝の言葉を添えるだけで、保護者のモチベーションや信頼関係は大きく変わります。
次月につなげる月案の反省と振り返り
月末には、作成した月案を振り返り、実践の結果を評価・反省します。このプロセス(PDCAサイクル)が、8月の保育の質を高めます。漫然と反省するのではなく、以下のような具体的な視点を持って自己評価を行ってみてください。
7月月案の振り返りチェックポイント
- 健康・安全:熱中症や大きな怪我なく過ごせたか? WBGTによる活動制限の判断は適切だったか? ヒヤリハットの共有は機能していたか?
- 個別の配慮:水が苦手な子に対し、無理強いせず、楽しめるような代替案や環境を提供できたか? その子のペースで水に親しむ姿が見られたか?
- 人間関係:玩具の取り合いなどのトラブルに対し、双方の気持ちを代弁する丁寧な関わりができたか? 子ども同士の言葉のやり取りが増えるような援助だったか?
- 環境構成:動線はスムーズだったか? 玩具の量は十分だったか? 静と動の切り替えができる環境になっていたか?
- 感染症対策:手洗い、消毒、タオルの管理などは徹底できていたか? クラス内で感染拡大を防ぐ手立ては十分だったか?
特に、7月の反省で多いのが「活動を詰め込みすぎて、子どもたちが疲れてしまった」という点です。子どもの表情や食欲、午睡の様子を観察し、活動量と休息のバランスが適切だったかを厳しくチェックし、8月の計画(時間の短縮や休息の増加など)に反映させていきましょう。
3歳児の7月月案作成のポイントまとめ
「3歳児の7月度月案」をテーマに、ねらいの設定から具体的な活動内容、書き方の文例まで、かなり詳細に解説してきました。
7月の保育は、子どもの体調変化に敏感になりながら、夏ならではのダイナミックな遊びを保障するという、非常に高度な「静と動のバランス感覚」が求められます。保育士さん自身も暑さで体力を消耗する時期ですが、プールでの子どもたちの弾けるような笑顔や、「冷たいね!」「見て見て!」と目を輝かせる姿は、何よりのエネルギーになるはずです。
安全管理という土台をしっかり作りつつ、子どもたちと一緒に先生自身も夏の楽しさを共有できるような、素敵な月案を作成してくださいね。

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。
しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。
また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。
選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。
参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。
厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。
少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。
地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。
そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。
参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?