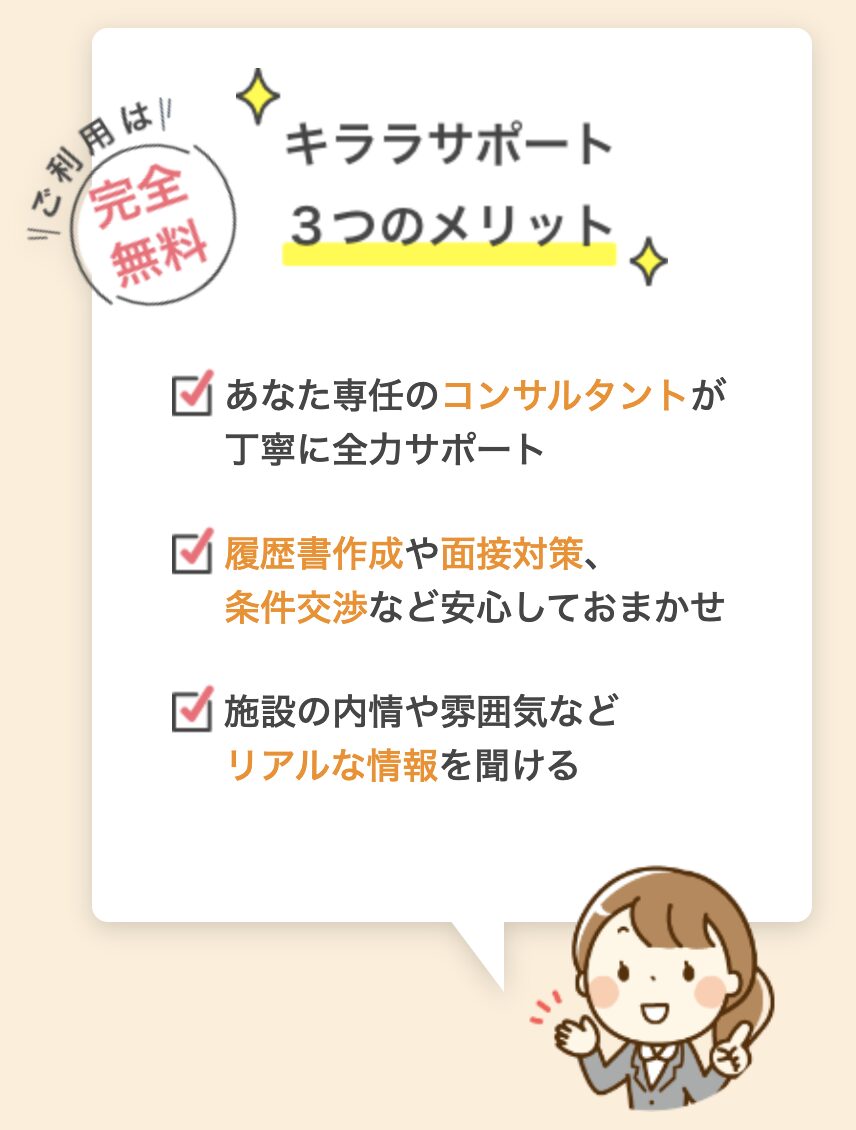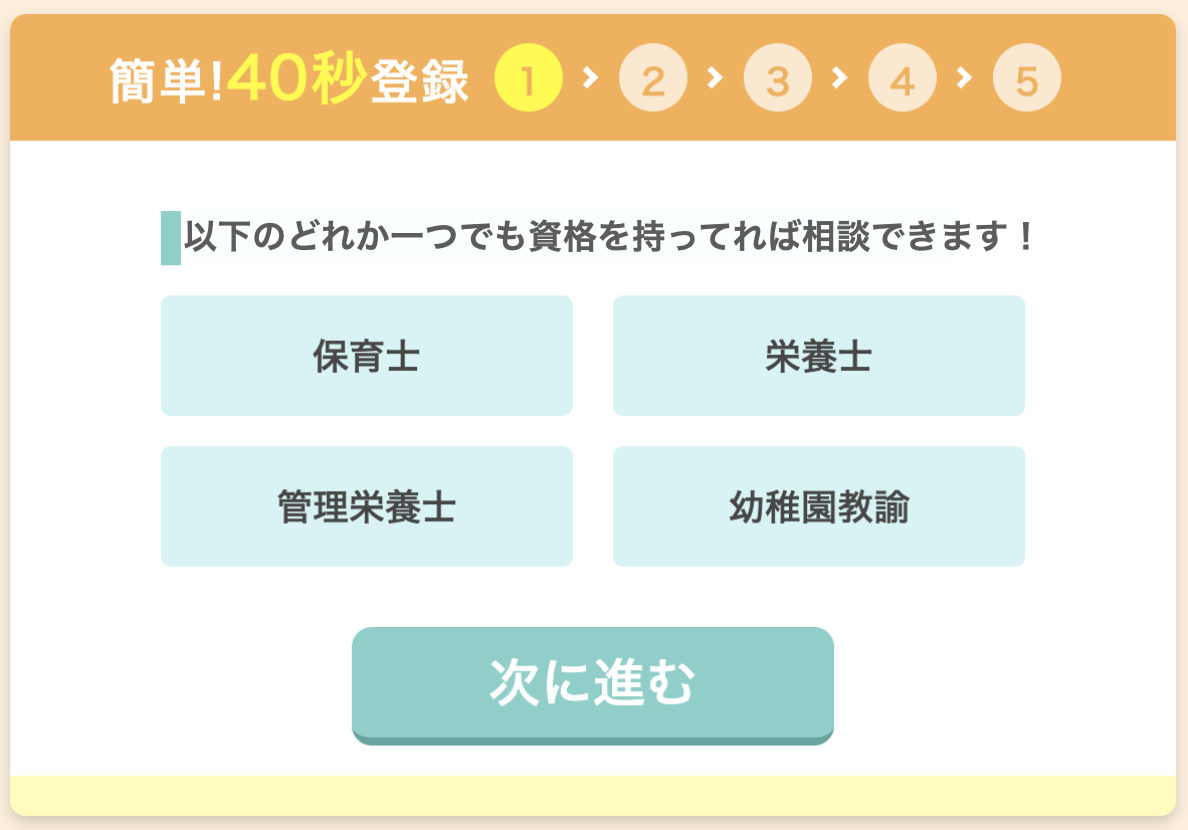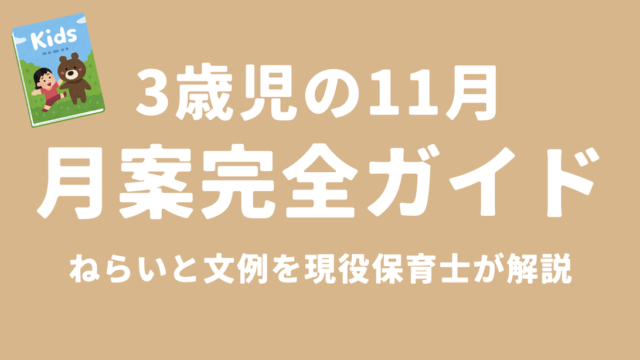1歳児の月案|7月の保育のねらいと五領域を丁寧に解説

7月は気温も湿度も高く、1歳児にとって過ごし方の工夫がとても重要になる時期です。「1歳児 月案 7月」を検索している保育者の方の中には、どんな活動を取り入れればよいのか、月案の書き方に迷っている方も多いのではないでしょうか。
特にこの時期は、子どもの心身の健康を守りながら、成長を支えるバランスの良い計画が求められます。
こんな悩みはありませんか?
- 7月にふさわしい月案の「ねらい」が思いつかない
- 「養護」と「教育」のバランスが取りづらい
- 「五領域」に沿った活動の組み立て方がわからない
- 日々の保育を「反省」して次に活かす視点が欲しい
- 保護者とのやり取りを円滑に進める「家庭との連携」の方法に悩んでいる
- 夏場の「生命の保持」や「健康管理」に不安がある
- 「食育」の取り入れ方がマンネリ化している
- 「環境構成」に工夫を持たせたいが時間が足りない
- 成長過程に合わせた「教育」の工夫がわからない
- 「子どもの姿」をどう記録・反映すればよいかわからない
- 「言葉」や「人間関係」への関わりが一方的になっていないか心配
- 「表現遊び」にどう広がりを持たせればよいか迷っている
この記事では、1歳児の7月にふさわしい保育の「ねらい」や、「養護」と「教育」の視点を交えながら、五領域の要素をどのように活動に取り入れていくかを具体的に紹介します。また、「家庭との連携」や「生命の保持」、「健康」への配慮といった基本的な対応にも触れ、日々の保育の中で無理なく実践できる工夫を解説しています。
1歳児の月案|7月に取り入れたい生活と保育の工夫

心地よく過ごすための養護のねらい
1歳児が安心して園生活を送るためには、「心地よく過ごすこと」が非常に大切です。この時期の子どもたちは、日々の生活の中でさまざまな変化や刺激に触れながら心と体を育んでいます。そうした中で、子ども一人ひとりが「ここにいて安心できる」と感じられる環境づくりが、養護における重要なねらいとなります。
まず、子どもにとって「心地よい」とは、ただ快適な気温や整った部屋というだけではありません。自分の気持ちが受け止められ、大人との信頼関係の中で過ごせることが前提になります。保育者が子どもの気持ちに寄り添い、泣いたときや戸惑ったときにすぐに反応することで、子どもは安心して感情を出せるようになります。
また、日々の生活リズムが整っていることも心地よさに直結します。1歳児の時期はまだ生活リズムが安定しきっていないため、睡眠・排泄・食事などの基本的な生活習慣を園で支えていく必要があります。例えば、午睡に入りやすいように静かな環境を整えたり、眠くなるタイミングを見逃さずにサポートしたりすることも大切な養護の一つです。
ただし、子どもによって快・不快の感じ方には個人差があります。そのため、「こうすれば全員が安心する」という一律の対応ではなく、日々の様子を観察し、子ども一人ひとりに合った援助をすることが求められます。ここでの注意点は、保育者が自分の判断で“心地よさ”を決めつけないことです。言葉にならないサインを見逃さないようにする観察力が求められます。
命を守る「生命の保持」の基本対応
1歳児の保育において、最も優先されるのは「生命の保持」です。まだ体力や免疫力が十分に発達していないこの年齢の子どもたちにとって、日常生活の中には多くのリスクが潜んでいます。したがって、保育者が安全と健康に対する強い意識を持ち、基本的な対応を確実に行うことが大前提になります。
まず重要なのは、日々の健康観察です。登園時には表情、皮膚の色、呼吸の様子などをよく観察し、普段と違う点がないかを見極めます。また、保護者とのやり取りを通して家庭での体調や変化を把握することも欠かせません。もし少しでも異変が感じられた場合には、職員間で情報を共有し、迅速に対応できるように備える必要があります。
さらに、園内での事故や怪我を防ぐための環境づくりも基本的な対応のひとつです。例えば、転倒しやすい場所にクッション材を置いたり、口に入れると危険な小さな物は手の届かない位置にしまったりといった物理的な安全対策は欠かせません。また、水遊びや食事など、事故のリスクが高まる場面では、必ず保育者がそばで見守るようにします。
一方で、子どもの自立心や挑戦したい気持ちを奪わないようにすることも大切です。命を守るというと、つい過剰に制限をかけてしまいがちですが、過保護になりすぎると成長の機会を奪ってしまうこともあります。そのため、安全な範囲で「やってみよう」という気持ちを応援する姿勢も忘れてはいけません。
また、感染症の流行が心配される夏場や冬場には、特に手洗いや消毒、換気といった衛生管理を徹底する必要があります。集団生活の中では一人の体調不良が他の子どもたちに広がる可能性もあるため、園全体でのルールや対応マニュアルを共有しておくことが大切です。
健康に過ごすための配慮ポイント
1歳児が園生活を健康的に送るためには、保育環境全体を通じて細やかな配慮が必要です。この年齢の子どもは、体温調節機能が未熟で、体調の変化が突然起こることもあります。そのため、気温や湿度、活動量などをこまめにチェックし、無理のない生活リズムを整えることが大切です。
例えば、暑い季節には室内の温度管理が非常に重要になります。エアコンを使う際には、冷えすぎや乾燥に注意し、子どもが快適に過ごせるように調整します。また、汗をかいたあとはすぐに着替えができるよう、替えの衣類を十分に用意しておく必要があります。こうした対応が、あせもや風邪といった体調不良の予防につながります。
さらに、活動と休息のバランスも健康維持には欠かせません。遊びに夢中になると疲れに気づかない子どもも多いため、適度なタイミングで休憩を入れるようにします。午睡の時間をしっかり確保し、ぐっすり眠れるような静かな環境づくりも大切な配慮の一つです。
一方で、保育者の判断だけで健康状態を決めてしまうのは危険です。普段の様子をよく知っている保護者との連携を通じて、より的確な対応が可能になります。朝の会話や連絡帳などを活用して、細かな変化を見逃さないようにすることが求められます。
また、集団生活の中では感染症のリスクも高まります。風邪や胃腸炎などの症状が見られた際には、他の子どもにうつさないように配慮し、必要に応じて保護者への早めの連絡や受診のお願いをすることも重要です。
夏に楽しむ食育と食への関心づくり
1歳児にとっての「食」は、単なる栄養補給の手段ではなく、心と体の成長に深く関わる大切な体験のひとつです。とくに夏は、食欲が落ちたり水分不足になりやすい季節ですので、食育の工夫がいつも以上に重要になります。この時期に合った食材や調理法を取り入れながら、「食べるって楽しい」という気持ちを育てていくことが目標です。
例えば、キュウリやトマト、オクラなどの夏野菜は、色や形、香りに特徴があり、見た目にも興味を持ちやすい食材です。保育の中では、これらの野菜を実際に触ってみたり、水をあげるお世話をしたりすることも可能です。こうした体験を通して、子どもたちは野菜を「知らないもの」から「身近で親しみのあるもの」として捉えられるようになります。
また、暑さによる食欲低下を防ぐには、無理に食べさせるのではなく、「一口でも食べてみようかな」と思える環境を整えることが大切です。保育者が「おいしいね」「シャキシャキしてるね」と声をかけることで、子どもが食事に対して前向きな気持ちを持ちやすくなります。身近な大人が楽しそうに食べている様子を見ることも、1歳児にとっては大きな刺激になります。
ただし、注意したいのは無理に食べさせようとしすぎることです。嫌いなものを口にしただけで吐いてしまったり、食事そのものに嫌悪感を持ってしまうこともあります。このようなときには、まずは触れる・においをかぐなどの関わりから始め、少しずつ慣れていけるように支援します。無理強いはせず、個々のペースを尊重することが大前提です。
夏の食育は、「食べることの意味」や「食べ物の背景」にもつながる学びのきっかけになります。水をあげて育てた野菜を自分の手で収穫し、その野菜が食卓に並ぶ——この一連の流れを経験することで、1歳児であっても小さな命の循環や自然への感謝に触れることができるのです。
ご家庭と連携して安心できる園生活を
1歳児の子どもたちは、園と家庭という異なる環境を行き来しながら生活しています。その中で安心して過ごすためには、家庭と園との連携がとても重要です。日々のやり取りの中で保護者と信頼関係を築き、子どもの育ちを一緒に見守る姿勢が求められます。
まず、毎朝の登園時や連絡帳を通じて、子どもの体調や家庭での様子を保育者がきちんと把握することが基本です。例えば「昨日は夜更かしをした」「今朝はあまり食べていない」といった小さな情報も、園での生活を整えるうえでは大きなヒントになります。このような情報があることで、子どもがぐずったり元気がなかったりした際も、その背景を理解したうえで対応することができるのです。
また、季節ごとの持ち物や服装の配慮も、家庭との協力が欠かせません。とくに夏は着替えの頻度が増えたり、水遊びの準備が必要になるなど、家庭側の理解と準備が必要になります。保護者に対しては、準備の理由や目的を丁寧に伝えることで、納得感を持って協力してもらいやすくなります。
一方で、すべてを保護者にお願いしすぎるのも避けたいところです。忙しい中での支度や連絡に対して、無理のない形でお願いする配慮も必要です。そのためには、簡潔でわかりやすい案内を心がけたり、必要な準備物は余裕を持って伝えたりするなど、保育者側の工夫も求められます。
そして何より大切なのは、子どもの育ちを中心に、家庭と園が「対等なパートナー」として関わることです。園での様子を一方的に伝えるのではなく、家庭での様子や悩みにも耳を傾ける姿勢を持つことで、保護者はより安心して園に子どもを預けることができます。
1歳児の月案|7月を通して見えてくる子どもの成長

教育活動と五領域のバランスを考える
1歳児の教育活動においては、五領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)を意識しながら、日々の生活や遊びを通して自然に育ちを促すことが重要です。この年齢の子どもは、「遊び」が最大の学びの場であり、その遊びの中に多様な体験や発見を含めることで、五領域の要素をバランス良く取り入れることが可能になります。
まず、「健康」の領域では、体を動かす活動が中心になります。例えば、園庭での追いかけっこや簡単な体操など、全身を使う遊びを積極的に取り入れることで、基礎体力や運動機能が育ちます。「暑い日は日陰で過ごす」など、無理のない活動設定を行いながら、心地よく体を動かせる環境を用意することも大切です。
次に、「人間関係」では、他児とのやり取りを通して相手の存在を意識する経験が増えていきます。「どうぞ」や「かして」といったやりとりの中で、少しずつ社会的なルールや感情の調整を学びます。この時期はまだ自己中心的な思考が強いですが、大人が間に入りながら見守ることで、自然な関わりが増えていきます。
「環境」に関しては、身の回りにあるものへ関心を持ち、自ら関わろうとする力を引き出します。水や砂、落ち葉や虫など、自然の中での体験は、子どもの好奇心を刺激します。遊びや活動に使用する道具や素材を工夫することで、より豊かな環境と出会えるようになります。
また、「言葉」や「表現」の領域は、感情や考えを伝える力、想像力を養ううえで欠かせません。歌や絵本、簡単な会話を通して言葉に親しみ、クレヨンや粘土などで表現することで、内にあるものを外へ出す練習にもなります。発達段階に応じて、ことばを発するタイミングや表現の幅も変わっていくため、子どもの反応をよく観察しながら支援することが求められます。
「ことば」に親しみ気持ちを伝える力を育む
1歳児にとって、「ことば」はまだ発展途上の能力ですが、日々の生活の中で育まれていく非常に大切な力です。この時期の子どもは、まだ自分の気持ちを上手く言葉で表現することができませんが、だからこそ周囲の大人の関わり方がその成長に大きく影響を与えます。
例えば、保育者が日常の動作にことばを添えて関わるだけでも、子どもは多くの表現を耳にし、吸収していきます。「靴はこうやって履こうね」「ジュース飲もうか」といったシンプルな声かけを繰り返すことで、言葉と行動が結びつきやすくなります。さらに、子どもが発した喃語や単語に対して保育者がしっかりと応答することが、安心感と意欲の両方を育てます。
また、絵本の読み聞かせや手遊び歌も、ことばへの親しみを深める大きな助けとなります。短くてリズムのあるフレーズ、音の繰り返しなどは、子どもにとって楽しく真似しやすいため、自然と口ずさむようになります。最初は保育者のまねをしていた言葉が、やがて自分の意思表示へとつながっていくのです。
ただし、言葉の習得には個人差があります。早くから話し始める子もいれば、しばらくはほとんど言葉が出てこない子もいます。焦らず、それぞれのペースを大切にしながら、「言いたくなる環境」を整えることが基本です。無理に言わせようとしたり、「まだ話せない」と心配しすぎたりするのは避けたいところです。
一方で、言葉が未熟だからこそ、誤解や不安を感じやすい時期でもあります。気持ちを伝えたいのに伝わらない、そんな体験を何度も重ねることで、泣いたり怒ったりといった反応になることも少なくありません。このようなとき、保育者が気持ちを代弁したり、「〇〇したかったんだね」と共感したりすることで、子どもは自分の感情を受け入れてもらえたと感じられます。
お友だちとの関わりを通じた人間関係の芽生え
1歳児にとって「友だち」という存在はまだ明確な意味を持っていないかもしれません。しかし、同じ空間で過ごし、同じ遊びを楽しむ中で、他の子の存在を少しずつ意識しはじめるようになります。この「なんとなく一緒にいる」「同じものに興味を持つ」という経験が、人間関係の芽生えの第一歩です。
この年齢の子どもたちは、まだ自分の気持ちや欲求を優先して動くことが多く、他児との関わりの中ではトラブルも頻繁に起こります。おもちゃの取り合い、押し合い、泣き出してしまう…ということも日常茶飯事です。しかし、こうした場面こそが「社会性」を学ぶ貴重な機会です。大人が介入しすぎず、けれど必要なときにはしっかりと仲立ちすることで、子ども同士のやり取りを見守っていく姿勢が大切です。
例えば、ある子がブロックを手に取り、近くにいた別の子が同じものを欲しがったとします。このとき、保育者が「かしてって言えるかな」「順番に使おうね」と声をかけることで、子どもは「相手の気持ちを知る」第一歩を踏み出します。もちろん、最初はうまくいかないことも多いですが、繰り返し経験することで徐々に相手の存在を認識し、「一緒に遊ぶって楽しい」と感じるようになります。
ただし、無理に「仲良くさせよう」としたり、「けんかしちゃダメ」と言いすぎたりするのは逆効果になる場合もあります。子ども自身が「どうしたらうまくいくか」を体験の中で見つけていけるよう、あくまで見守る姿勢を持つことが重要です。時にはトラブルから少し離れる時間を作ったり、自分の遊びに集中できる空間を用意することも、有効な手立てになります。
この時期に育まれる人間関係の力は、将来的な集団生活や社会性の土台となるものです。1歳児という幼い時期であっても、他者との関わりを通じて「嬉しい」「楽しい」「くやしい」といった感情のやり取りを重ねることで、心の中に小さな社会性の芽が育っていきます。
感性を育てる表現遊びの工夫
1歳児にとって「表現」とは、言葉や動作だけでなく、全身を使った感情のアウトプットそのものです。この時期の子どもたちは、自分の気持ちをうまく言葉で伝えることが難しいからこそ、感覚を通して感じたことを、動きや音、色、形などで自由に表そうとします。表現遊びは、そうした内面の育ちを促すための大切な活動です。
このような遊びでは、まず“できばえ”よりも“過程”を大切にします。例えば、クレヨンでただ線を引くことも、子どもにとっては「今、この色を使ってみたい」「手を動かすのが楽しい」といった感性の現れです。保育者が「じょうずに描けたね」と結果を評価するよりも、「たくさん動かしたね」「赤が好きなのかな」と、気持ちに寄り添う声かけを意識することで、子どもは安心して表現することができます。
表現の幅を広げるためには、素材や道具の工夫もポイントです。紙だけでなく、段ボール、布、スポンジ、氷など、さまざまな質感に触れられる素材を使うことで、感覚をより豊かに刺激できます。例えば、寒天をつぶす遊びは、冷たさ・やわらかさ・色の鮮やかさなど、多くの感覚を同時に刺激し、子どもたちの想像力を広げるきっかけになります。
ただし、こうした遊びには準備や片付けの手間がかかるため、保育者の負担が増えることも事実です。また、汚れを嫌がる保護者もいるかもしれません。その場合には、活動のねらいや楽しさ、子どもの反応を丁寧に伝え、保護者にも理解してもらえるようなコミュニケーションを図ることが大切です。
子どもの姿から読み取る育ちのヒント
日々の保育の中で、子どもたちが見せる行動や表情には、小さな成長のサインがたくさん隠されています。その一つひとつに丁寧に目を向けることで、保育者はその子の「今」の姿だけでなく、「これから」の育ちを考えるヒントを得ることができます。
例えば、「自分で靴を履こうとしている」「友だちのそばに自然と寄っていく」など、一見ささいに思える行動であっても、それは大きな成長の兆しです。これまで大人の手を借りていたことを自分でやってみようとする姿は、自立の芽生えであり、周囲への関心を持ち始める様子は、社会性のスタートラインに立っているとも言えます。
こうした成長は一人ひとり違ったペースで訪れます。同じクラスにいても、言葉が早い子、身体の動きが活発な子、感情の表現が豊かな子など、得意なことや関心はさまざまです。そのため、全員に同じ目標を求めるのではなく、その子らしさを認めたうえで「この子には今どんな支援が必要か?」を考える視点が求められます。
観察の中では、ただ行動を記録するだけでなく、「なぜその行動をしたのか」「背景にどんな気持ちがあるのか」を想像する力も必要です。例えば、友だちにおもちゃを貸せなかった場面では、「まだ貸し借りの意味が分からないのかもしれない」「自分のものという意識が育ってきた証かもしれない」といったように、多面的に読み取っていくことが大切です。
また、子どもの成長は一進一退です。昨日できたことが今日はうまくいかない、そんな場面も多く見られます。そういったときに、「後戻りした」と捉えるのではなく、「今は立ち止まって、次のステップを準備している時期なんだ」と考えることで、保育者の関わり方も自然と変わっていきます。
月末の反省で来月につなげる振り返り
月末に行う「振り返り」は、ただ反省点を並べるだけの作業ではありません。むしろ、子どもたちと過ごした一ヶ月を丁寧に見つめ直し、次の月へどうつなげていくかを考えるための大切な時間です。保育者自身の気づきや子どもの変化に注目しながら、実践を見直すことによって、よりよい保育へと結びついていきます。
まず、振り返りの際には、計画した活動と実際の子どもの姿を比較してみましょう。例えば、水遊びを多く取り入れたけれど、思ったほど集中できなかったと感じた場合には、「環境の設定が適切だったか」「子どもの興味を引く仕掛けが足りなかったか」といった具体的な観点で見直します。活動がうまくいかなかったからといって失敗と決めつけず、その背景を探ることが大切です。
一方で、思いがけない子どもの反応から学ぶこともあります。「こんな遊び方をするなんて予想外だった」「自分からお友だちに話しかけるようになった」など、保育者の想定を超える姿に出会うことも少なくありません。こうした気づきは、次の計画に大いに役立ちます。
また、反省という言葉にはネガティブな印象を持つかもしれませんが、本来は「何が良かったか」も同時に見つめ直す作業です。「今月は無理なく過ごせた」「保護者とのやり取りが増えた」など、うまくいった点を意識することで、自信にもつながります。
さらに、振り返りを職員同士で共有することも大切です。一人では気づかなかった視点に出会ったり、他のクラスの取り組みを参考にしたりすることで、保育の幅が広がります。加えて、家庭とのやり取りの中で得られた情報も取り入れると、子どもの全体像をより深く理解することができます。
1歳児 月案 7月に取り入れたい保育のポイントまとめ

記事のポイントをまとめました。
- 子どもが安心して過ごせる信頼関係と環境づくりが重要
- 快適な生活リズムを支える養護的配慮が求められる
- 健康観察を通して体調の変化を早期に捉えることが大切
- 園内の事故予防には物理的・人的な安全対策が必要
- 水遊びや食事中などリスクが高まる場面では常に見守りを強化する
- 感染症対策として手洗い・消毒・換気を徹底する
- 気温や湿度に応じた室内環境の調整が欠かせない
- 食欲が落ちる夏でも無理なく楽しめる食育の工夫が有効
- 夏野菜を用いた体験活動が食への興味を高める
- 保護者とのこまめな情報共有が安心な園生活の鍵となる
- 登園時のちょっとした会話が保育の質を左右する手がかりになる
- 五領域をバランスよく組み込んだ活動が学びの広がりにつながる
- 絵本や手遊び歌を活用して言葉への親しみを育てる
- 他児との関わりを通して社会性の芽生えを支える
- 月末の振り返りを次の計画に活かす姿勢が保育の質を高める

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。
しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。
また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。
選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。
参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。
厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。
少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。
地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。
そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。
参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?